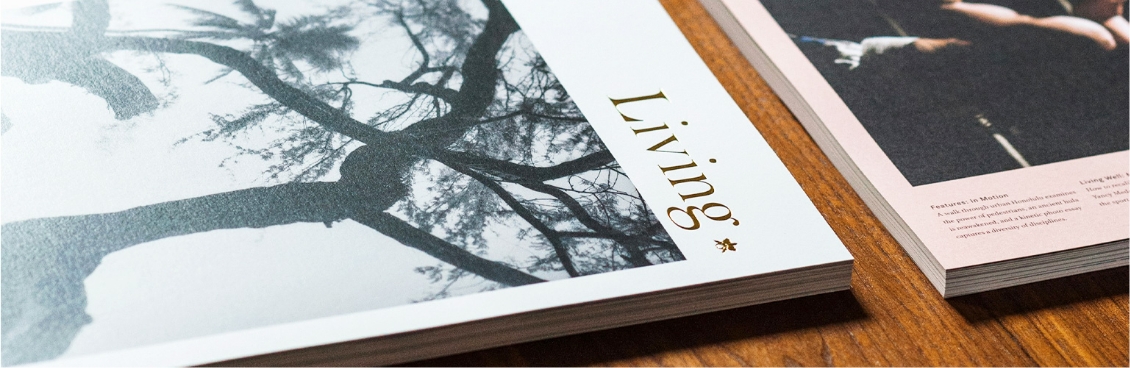
ブログ
2025.09.06
耐震とバランス

耐震性を高めるために大切なこと 〜設計段階でできる具体策〜
おはようございます。
Tsumugu Houseの新内です。
日本は世界有数の地震大国です。
ここ最近の地震傾向を見ても、震度7クラスが一度で終わらず、
複数回続くケースが多くなってきています。
また、3〜4の余震がその後も何度も発生しています。
このような現実を前に、住宅の耐震性をどこまで高められるかは
「命を守るための設計」と言っても過言ではありません。
今回は、高い耐震性を実現するために設計段階で知っておくべきポイントを、
3つの観点からお伝えします。
✔️まずは「平屋を基本」として考える
一般的に、同じ構造・仕様であれば平屋の方が耐震性は高くなります。
なぜなら、2階建ての家は以下のような構造上のデメリットがあるからです:
- 1階には大空間をつくりたいため柱や壁が少なくなりがち
- 2階には部屋を複数つくるため柱や壁が多く、重くなる
- 結果として**下が弱く、上が重い
「アンバランス構造」**になりやすい
また、大きな開口部(窓)を1階に多く設けると、
その分壁量が減り耐震性はさらに低下します。
✅ 敷地の都合で2階建てにする場合は…
- 1階と2階の柱位置は60%以上一致させる
- 1階と2階の壁の位置は50%以上一致させる
この2点をしっかり意識して、構造のバランスを保つように設計しましょう。
✔️「壁のバランス」が何より大切
耐震性において、最も重要なのは壁の量ではなく「バランス」です。
例えば、家の南側ばかりに窓を設けて採光を確保しようとすると:
- 南側:窓だらけで壁が極端に少ない
- 北側:窓がなく壁が多い
このような構造では南北の壁量のバランスが大きく崩れ、
地震時にひずみやすくなるのです。
さらに、2階にバルコニーを張り出すと、
階の南側に負担が集中しバランスはさらに悪化します。
✅ 重要なのは「壁量」より「壁配置のバランス」
構造的に強い家を目指すなら、
壁を単に増やすのではなく:
「壁が四方にバランスよく配置されているか?」
この視点が欠かせません。
設計士としっかり相談して設計に反映させましょう。
✔️「中庭の家=耐震性が低い」は本当?
時折、「中庭のある家は耐震性が弱いのでは?」という声をいただきます。
確かに中庭によって内部の壁量は減るかもしれません。
しかしその分、外周部の採光が不要になるため、
窓を減らして壁を増やせるという利点があります。
✅ むしろ「中庭のある平屋」は耐震性に有利な条件が揃う
- 四方の外壁にしっかりと壁を設けられる
- 壁量だけでなく配置バランスも良くなる
- 採光とプライバシー、耐震を両立できる
加えて、平屋にすれば上からの荷重も軽減されるため、
全体的な揺れに対する強さも格段に向上します。
さらに、耐震等級3を取得しやすく、
構造設計の自由度も保てます。
【まとめ】最も大切なのは「設計バランス」
- 耐震等級を上げる
- 制震装置を取り入れる
- 金物の設置で強度を上げる
こうした要素ももちろん大切ですが、
設計時点で「荷重と壁のバランスが取れているか」
を最優先で考えることこそ、最も地震に強い家をつくる鍵だと私たちは考えています。
家づくりを進める上で、「バランスのとれた設計か?」という視点を、
ぜひ忘れずにお持ちください。
それではまた・・・。


