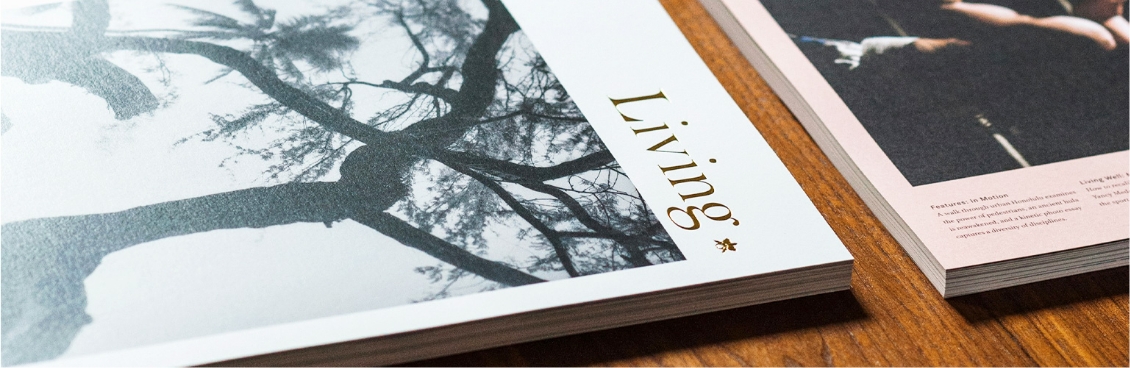
ブログ
2025.08.09
家づくりのコスト削減法(維持管理続編)

固定資産税・火災保険も「建てる前」が勝負
前回は、電気代を抑えるために必要な知識についてお伝えしましたが、
家を持つ限りかかり続ける費用は、それだけではありません。
今回は、固定資産税と火災保険について、
建てる前に知っておくだけで将来的な負担を
大きく減らせるポイントをお伝えします。
おはようございます。Tsumugu Houseの新内です。
固定資産税は「土地の広さ」で大きく変わる
まず、固定資産税について。
土地の広さが200㎡(約60坪)以下か、それを超えるかによって、
税金の計算方法が大きく変わります。
- 200㎡以下の部分は、課税評価額が6分の1
- 200㎡を超える部分は、課税評価額が3分の1
つまり、200㎡を境に超えた部分の税額が約2倍になってしまうのです。
たとえば評価額が18万円/坪の土地を100坪購入した場合:
- 60坪:3万円×60坪×1.4%=25,200円
- 残り40坪:6万円×40坪×1.4%=33,600円
→ 合計:58,800円/年
このように、評価額の違いにより毎年の固定資産税に差が出ます。
不要な税負担を避けるためにも、
土地面積は60坪以内に抑えることをおすすめしています。
ちなみに、60坪あれば、
- 車を3〜4台停めるスペース
- 子育て世代がゆったり暮らせる平屋住宅
など、十分な暮らしが実現できます。
岡山市なら「都市計画税」にも注意
もう一点、一部地域にかかる特有の税制度についても触れておきます。
岡山市の「市街化区域」に該当するエリアでは、
固定資産税に加えて都市計画税が課税されます。
この都市計画税も、固定資産税と同じく、
200㎡以下かどうかで課税評価額が大きく変わるため注意が必要です。
土地選びの際は、金額だけでなく、
その土地が市街化区域かどうか・面積が200㎡を超えるかどうか
という視点でも判断することが大切です。
火災保険は「構造」によって2倍以上の差が
次に、火災保険について。
火災保険料は、建物が
「非耐火構造」か「省令準耐火構造」かで、大きく金額が変わります。
たとえば省令準耐火構造にすることで、
火災保険料は半額以下になることもあります。
また火災保険は、建物本体だけでなく、
家財道具にもかける方が多いため、
構造の違いによる影響は、さらに大きくなります。
さらに、地震保険にも加入を検討されている場合、
省令準耐火構造の方がやはり保険料を大幅に抑えられます。
地震保険料を安くするもう一歩「耐震等級3」
地震への備えとして地震保険を検討しているなら、
耐震等級3を取得することも視野に入れてみてください。
耐震等級3を取得すると、
地震保険料がさらに約半分にまで抑えられる可能性があり、
安心とコスト削減を両立できます。
また、万が一の際には、
家財の方が保険金が下りやすい傾向があるため、
余力がある場合は、建物だけでなく家財にも保険をかけることをおすすめします。
保険の加入は「備え」と「バランス」
もちろん、保険はあくまで「もしもの備え」ですので、
「入りすぎはもったいない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、必要最低限の火災保険のみにするという選択肢もあります。
どこまで備えるかは、ご家族のライフスタイルや考え方によって異なるものです。
ぜひご家庭でよく話し合った上で、納得のいく選択をしてください。
「建てた後のコスト」にも目を向ける
家づくりでは、建築費やローンの金利など、
目の前のコストに目が行きがちですが、
建てた後にかかるコストを見落としてはいけません。
固定資産税・火災保険・地震保険など、
長期的に支払いが続くランニングコストも視野に入れたうえで、
賢く、そして納得のいく家づくりをしていただければと思います。
それではまた・・・。


