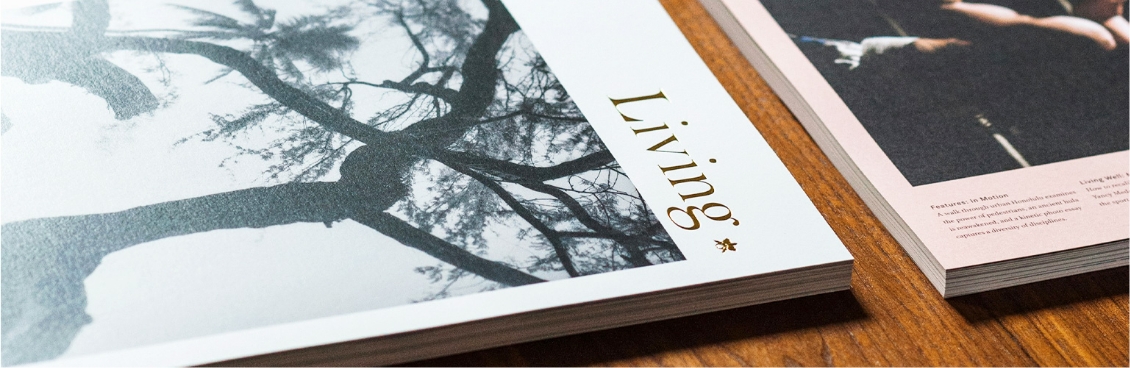
ブログ
2025.08.02
家づくりのコスト削減法(建築編4)

こんにちは。
Tsumugu Houseの新内です。
「収納は多ければ多いほどいい」
新築を考え始めた方の多くが、
そうお感じになるのではないでしょうか。
というのも、現在の住まいで収納が足りず、
部屋が散らかってしまったり、
物に圧迫されて窮屈さを感じていたりすると、
「次こそは収納をたっぷり確保したい」
と思うのも自然なことです。
さらに、先に家を建てた友人や知人から、
「もっと収納をつくっておけばよかった…」という声を聞けば、
なおさら、収納に過敏になってしまうのではないでしょうか。
ですが、実は収納も「作りすぎ」は注意が必要です。
面積を取りすぎると、建築コストが上がり、
その結果、住宅ローンの負担が大きくなったり、
将来の貯蓄や積立投資の余力を
削ってしまうことにもなりかねません。
また、作り方によっては、
「コストだけ増えて、実際の収納量はさほど変わらない」
という、もったいない状態に陥ることもあるのです。
収納でまず大切なのは「管理のしやすさ」
まず知っていただきたいのが、
収納は「管理のしやすさ」が命、ということ。
たとえば、多くの住宅で採用されている収納の奥行きは約91cm。
ですが、実際の持ち物のほとんどは、
**その半分(45cm程度)**の奥行きで十分収まります。
奥行きが深すぎると…
- 手前の物が邪魔で奥の物が取り出せない
- 奥に置いた物の存在自体を忘れてしまう
という事態が起こりがちです。
つまり、**「使いづらくなる=収納が活かせない」**ということですね。
奥行きを浅く、幅を広くするだけで収納量アップ!
この問題の解決策はシンプルです。
奥行きを浅くし、幅を広くする。
これだけで、床面積を増やすことなく、
収納の「量」と「使いやすさ」が一気にアップします。
さらに、天井高(約2.4m)を有効活用して、
棚板を5段にすれば、壁面の余白なく、
縦方向にもたっぷり収納できます。
具体的に比較してみましょう:
- 【奥行き91cm × 幅91cm × 棚2段】→ 約2.73mの収納量
- 【奥行き45cm × 幅182cm × 棚5段】→ 約10.92mの収納量
床面積はどちらも同じなのに、収納量は約4倍に。
このように、収納は「面積」ではなく「設計」で差がつきます。
だからこそ、“床”よりも“壁”をどう使うかがとても重要なんです。
✔ 「通り抜け動線」の落とし穴
もうひとつ、収納計画で知っておいていただきたいのが
「通り抜け動線」についてです。
最近は、ウォークスルー型の収納が人気ですが、
通り抜けできる収納にすると、
多くの場合、収納量が減ってしまいます。
たとえば、3帖(約5.2mの壁面がある)収納に通路を通すと…
- 出入り口のドアまわりには物が置けない
- 通路となる部分の壁面にも収納ができない
- ドアが1枚増えることでコストもアップ
- 照明のスイッチを2箇所切りにしたり、
センサーにしたりとさらにコスト増
つまり、便利さと引き換えに、
「収納量の減少」+「コスト増加」が同時に起こるということです。
ですので、「本当に通り抜けが必要か?」
をしっかりと見極めた上で、
設計に取り入れることが大切です。
最後に
収納に関しては、「多ければ安心」と思われがちですが、
“量”よりも“質”、
つまり管理のしやすさや使い勝手を重視することが、
快適な暮らしへの近道です。
そして、床面積をやみくもに広げるのではなく、
どう配置するか、どう設計するかで、
同じスペースでも大きく差が生まれます。
新築の計画に入る前に、
ぜひ「正しい収納の見方と作り方」
を知っていただけたらと思います。
次回は、これまでの「部屋の数」「広さ」「収納」を踏まえて、
間取りの最適な組み立て方についても
お伝えしていければと考えています。
それでは、また・・・。


